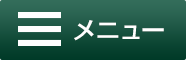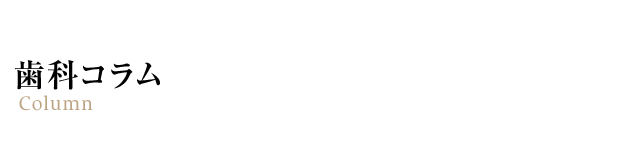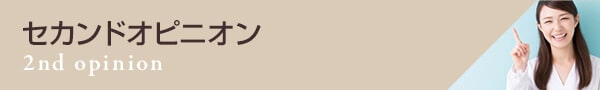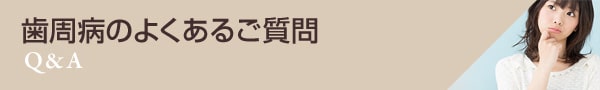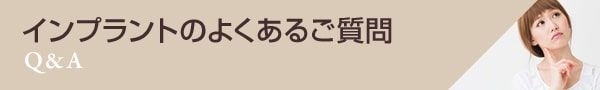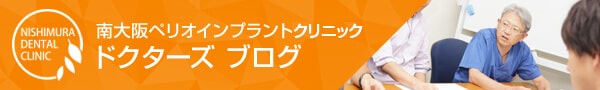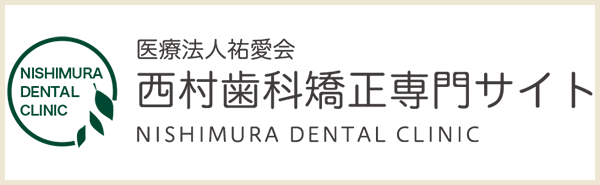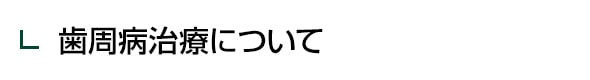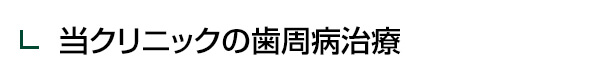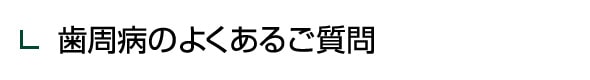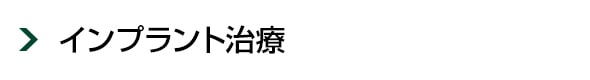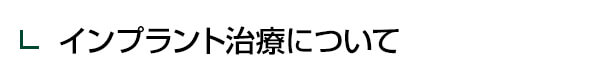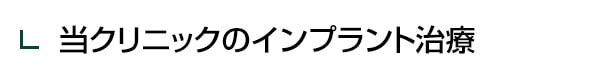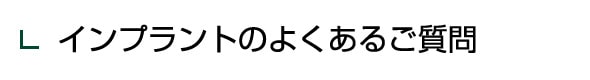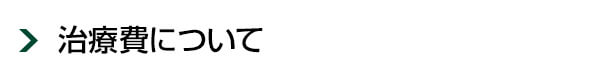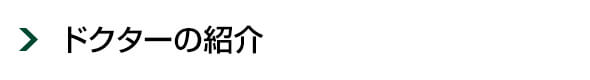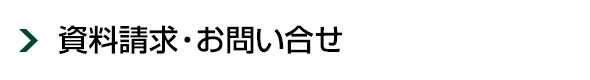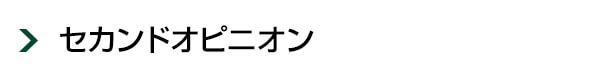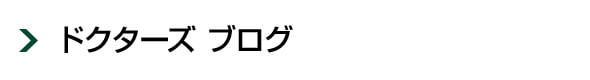インプラント治療は失敗するの?原因と対策についてわかりやすく解説
インプラント治療は、自分の歯に近い感覚や見た目、噛み合わせを取り戻すことができるというメリットですが、反対に失敗する可能性もあります。インプラント治療で失敗すると、どのような問題が起こるのでしょうか?
本コラムでは、インプラント治療で失敗しないために知っておきたいことや、失敗から学ぶことについて紹介します。事前になぜ失敗したのかを学んでおけば、より慎重に歯科医院選びができるようになるでしょう。
インプラントが骨と結合しない
インプラントの失敗例として、手術で埋め込んだインプラントが顎の骨と十分に結合しない場合があります。
この現象はオッセオインテグレーションの不全と呼ばれ、インプラントが安定せず、最終的に抜け落ちる原因となります。
骨と結合しない原因は一つではなく、骨の質が悪い、手術時の初期固定が不十分、細菌感染、喫煙、糖尿病などの全身疾患といった複数の要因が考えられます。
インプラントが結合しないという問題が起きた場合でも、その原因を特定し、適切な処置を行えば再度手術をすることは可能です。
多くの場合、インプラントを除去し、骨の状態が改善するのを待ってから改めて埋入することで、良好な結果が期待できる例もあります。
骨が足りなかった
インプラントを支えるためには、十分な量と質の顎の骨が必要です。
骨の量が不足している、あるいは骨密度が低く柔らかすぎる場合、インプラントをしっかり固定できず、骨との結合がうまくいかないことがあります。
逆に、骨が硬すぎる場合も血流が悪くなり、結合を妨げる要因となり得ます。
事前の検査で骨が足りないと判断されたにもかかわらず、骨を増やす処置をせずに手術を進めると、失敗のリスクが高まります。
もし骨の不足が原因で結合しなかった場合は、インプラントを一度除去し、骨造成手術を行ってから再度インプラントを埋入する処置が必要になるケースが考えられます。
事前のCT撮影による精密な診断が、このような失敗を避ける鍵となります。
細菌感染
インプラント治療において細菌感染は、失敗の大きな原因の一つです。
手術中や手術後にインプラント周辺で細菌が繁殖すると、炎症を引き起こし、痛みや腫れ、膿が出るなどの症状が現れる場合があります。
この状態は「インプラント周囲炎」と呼ばれ、歯周病に似た病態です。
感染が進行するとインプラントを支える顎の骨が溶かされ、最終的にはインプラントがぐらついて抜け落ちてしまいます。
細菌感染の原因としては、手術環境の衛生管理の問題、術前の歯周病治療が不十分だったこと、あるいは治療後のセルフケアや定期的なメンテナンス不足が挙げられます。
自覚症状が出にくい場合もあるため、歯科医院での定期的なチェックが不可欠です。
痛み、腫れ、しびれが続いている
インプラント手術は外科処置のため、術後に一時的な痛みや腫れが生じるのは正常な反応です。
しかし、これらの症状が1週間以上経過しても改善しない、あるいは悪化する場合には何らかの問題が起きている可能性があります。
特に下顎の奥歯の手術をした後、唇や顎にしびれや麻痺が残る場合、顎の骨の中を通る下歯槽神経を損傷したことが原因として考えられます。
これは、インプラントを埋め込むドリルの操作や、インプラント体の位置が神経に近すぎることによって発生します。
神経の損傷とは重大な問題であり、回復までに長期間を要したり、後遺症として症状が残ったりするケースも報告されています。
事前のCT検査で神経の位置を正確に把握した上で、安全な手術計画を立てることが極めて重要です。
インプラントが破損する・外れる
インプラント本体や上部構造(被せ物)が破損したり、外れたりするのも治療後のトラブルの一つです。
インプラントには、天然歯にある「歯根膜」というクッションの役割を果たす組織がありません。そのため、噛む力が直接インプラントと骨にかかります。
歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、過大な力がインプラントに加わり続け、被せ物のセラミックが欠けたり、インプラント本体と被せ物をつなぐネジが緩んだり、最悪の場合はインプラント自体が破損したりすることがあります。
このようなトラブルを避けるためには、噛み合わせの調整を精密に行うことや、就寝時にナイトガードを装着して歯ぎしりからインプラントを守るなどの対策が必要です。
定期的なメンテナンスで噛み合わせのチェックを受けることも欠かせません。
インプラント治療で失敗しないために知っておきたいこと
インプラント治療は高度な技術と専門知識を要するため、よい歯科医師に出会うことが治療の結果に大きな影響を与えるといっても過言ではありません。また、歯科医院を選ぶ際は、実際に治療を受けた方からの評価をチェックすることも、重要なポイントの一つです。治療に臨む前には、自身の期待や不安、疑問を医師にしっかり伝えてください。不安を解消したうえで治療の方向性をより明確できれば、満足度の高い治療を受けることができるでしょう。
このように、事前に治療に関する知識をしっかりと理解し、歯科医師とのコミュニケーションを深めることで、失敗するリスクを大幅に減少させることができます。
インプラント治療の失敗から学ぶこと
インプラント治療は、治療の難易度によって失敗する可能性もあります。また、患者さまがアフターケアを怠ったため、治療が失敗するケースもあります。ここでは、具体的な症例を参考に、なぜ失敗したのかをみてみましょう。
- 事例1:アフターケアを怠ったことによりインプラント周囲炎を発症
- 患者さまがアフターケア(ブラッシングやフロスをつかったセルフケア)を怠った結果、インプラント周囲炎を発症しました。その影響で歯茎が下がり、インプラントが露出する状態となり、結果的にインプラントを除去しなければなりませんでした。
- 事例2:骨造成(GBR)の失敗により、インプラント治療ができなかったケース
- 患者さまの顎の骨がインプラント治療に適していないため、骨造成(GBR)を用いた治療を実施。しかしこの過程で、担当医の技量に問題があり、骨の増加が想定以下となった結果、インプラント治療が実施できませんでした。
これらの事例は、インプラント治療における適切な診断、施術、そしてアフターケアの不可欠性を物語っています。治療を失敗しないようにするためには、事前の情報収集と、信頼できる歯科医師と綿密なコミュニケーションが必要不可欠です。他院でインプラント治療が難しいといわれた方は、ぜひ南大阪ペリオインプラントクリニックへお越しください。
- Q1:インプラント治療の成功率はどのくらいですか?
- A1:一般的に、インプラント治療の成功率は非常に高く、90%以上と報告されています。しかし、治療の成功は適切な手術手技やアフターケア、患者さまの全体的な健康状態など多くの要因に依存します。
- Q2:インプラントが失敗した場合、再度インプラント治療を受けることはできますか?
- A2:多くの場合、問題を特定し対処したのち、再度インプラント治療を受けることは可能です。ただし、十分な骨量が必要な場合は、骨増大手術(GBR法)が先に必要となることがあります。